Spotlights
未経験から正規雇用を生み出す6500億円市場――ROXX中嶋社長が語る「ノンデスクワーカー転職」への挑戦
未経験から正規雇用を生み出す6500億円市場――ROXX中嶋社長が語る「ノンデスクワーカー転職」への挑戦

株式会社ROXX 代表取締役社長 中嶋汰朗 氏
学生時代にハードロックバンドでデビューを目指し、起業前は渋谷のパスタ店でアルバイト経験しかなかった中嶋汰朗氏。そんな異色の経歴を持つ起業家が手がけるのは、年収200万円台のノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」だ。
2024年に上場を果たしたROXXの代表として、競合不在の巨大市場に挑む中嶋氏に、事業変遷の軌跡と上場後の現実、そしてAI時代における労働集約型ビジネスの可能性について聞いた。
Q1. なぜ「ノンデスクワーカー市場」に着目したのか
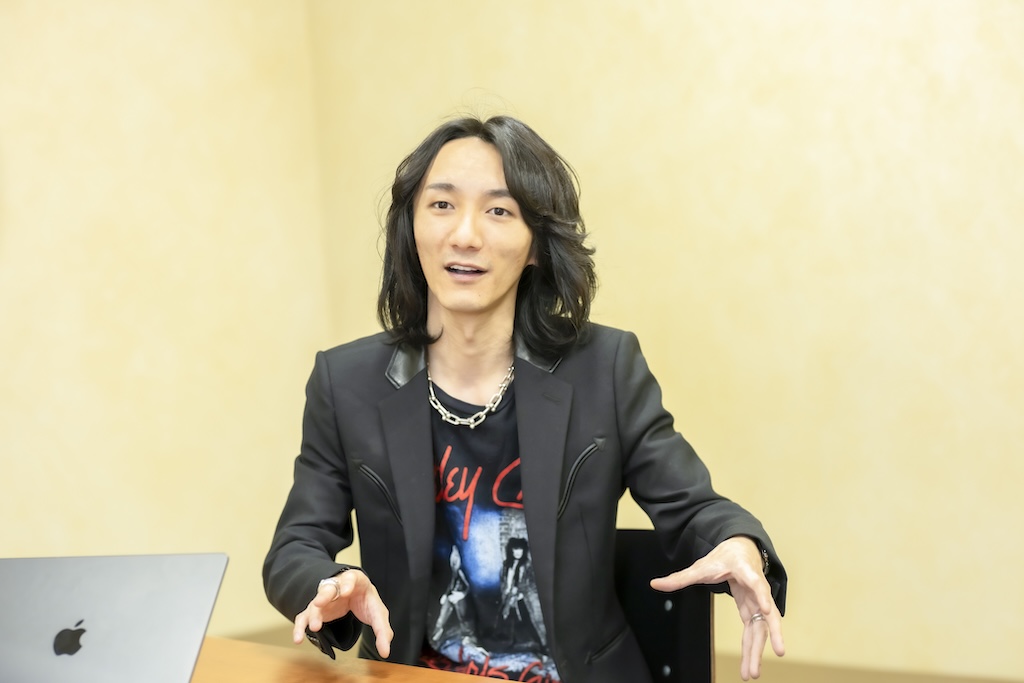
自分の身近な環境こそが、最大のヒントだった
――ROXXといえばリファレンスチェックサービスの「back check」で注目を集めましたが、現在の主力事業は転職プラットフォーム「Zキャリア」です。この事業転換はどのような経緯だったのでしょうか。
実は最初に手がけたのは「SCOUTER」というサービスで、約2.5億円投資して2年弱で立ち上がらなかった苦い経験があります。そこからback checkが注目されたのですが、実はその裏で、今のZキャリアの前身である「agent bank(現・Zキャリア プラットフォーム)」という紹介会社向けのサービスがずっと伸びていたんです。
SCOUTERは結論失敗に終わりましたが、その過程でさまざまな転職支援をしてきた中で、ずっと安定してマッチングしていたのが「学歴職歴を問わない企業」と「あまり働いたことがない人」の組み合わせだけだったんですね。
キャリアがある方だとなかなかマッチングしないんですが、学歴職歴不問の領域だけは毎月安定してデータが出ていました。そこを主軸に事業を開始したのがagent bank(Zキャリア プラットフォーム)でした。
――それは偶然の発見だったのでしょうか。
考えてみれば、僕の周りもみんなそんな感じだったんです。起業前はバンドをやっていたし、将来を見据えて就職するというよりも20代は好きなことをして、バイトでも派遣でも何でも、要は好きな時間に働いて生活している人たちが周りにいっぱいいた。そういう大人がもっと世の中に沢山いてもいいと今でも僕は思ってる部分があります。
一方で、徐々に年を取ってくると「やっぱりちゃんと働かなきゃ」ってなる人も沢山いた。結婚を考えたり、周りもさすがにまだフリーターを続けているのはどうかとか。最初はそれでよくても一生続くものではなく、年齢や環境で考え方も変わってくる。
僕自身、起業する前は友人が働いていた渋谷のパスタ店で時給850円、交通費なしで働いたことしかなかった。髪も背中まであって金髪で、そこしか雇ってくれなかった。でも当時はそのスタイルの方が大事だったし、そういった人たちのことはよく分かっているつもりです。
起業から一貫して人材業界に身を置き続けている中で、当時はビズリーチのようなハイクラス向けサービスが注目されていました。一方で、自分たちのサービス上で成果が出ていたのは、これから正社員になろうとしているけれど、そもそもやりたいことが見つからない人たち。
それから当時、そういった経験を問わずに正社員採用をしている顧客企業に聞いてみると「年間2,000人採用します」「5,000人採用します」という想像の何倍もの大きな規模での採用ニーズがあった。そこを深掘りした結果、未経験x正社員というターゲットに行き着いた。
Q2. 競合がいない理由と市場の変化

求人広告から成果報酬へのシフトが追い風に
――これだけ大きな市場なのに、なぜ他社が参入してこなかったのでしょうか。
ここまで人手不足が深刻になる以前は、採用媒体、いわゆる求人広告に100万円出稿すれば50人応募があって10人採用できていた時代がありました。つまり求人広告で安く採用できた時代だった。一方で少子化の影響や、大型の求人メディアが台頭したことで、今まで通り媒体にお金を払っても人を採用することができなくなってきた。
一方でそこを成果報酬でやってくれる会社はというと、当時はなかった。なぜなら単価が安すぎて、大手企業からするとあえてそこをやる理由がなかったからです。多くの人材紹介事業はハイクラス領域に向かっていましたが、労働市場の構造が大きく変化する中で、いち早く参入できたという背景です。
――現在のターゲット層について詳しく教えてください。
今、Zキャリア登録者の平均年収は約250万円で、手取りで言うと16万円程度です。7割がパソコンを持っていなくて、半数以上が高卒という中で、将来を考えて就職やキャリアアップをしたいけれど、目先の生活をまず何とかしなければならない、という方々に多く使っていただいています。
ただ、今の市場環境(※取材時は2025年5月)だと転職するだけでも年収は平均して約54万円も上がるという実績が出ています。
未経験の募集でも、競争環境が激しくなった中で、募集条件が年々良くなっていて、年収のスタートが300万円以上という求人が圧倒的に多いです。学歴不問で、休みもしっかり取れて、教育環境もあって、髪色やネイルといった自身のスタイルを変えなくても働けたり、タトゥーOKな求人が増えている。人手不足によって、求職者に選んでもらうために条件や要件が年々求職者ファーストに変わってきている。ここ数十年の中でも買い手市場から売り手市場に変わる中で大きな変化が生まれてきています。
Q3. 赤字上場という困難な選択をした理由

上場を牽引した「Zキャリア」
仲間との約束と外部資本への責任
――2024年9月に上場されましたが、M&Aという選択肢は考えなかったのでしょうか。
僕はなかったです。複数理由があって、1つは僕が同級生を巻き込んで創業に参加してもらって、みんなで死に物狂いでやってきたわけだから、自分だけが成功するようなイグジット(※保有株の売却)は絶対にしたくなかった。
スタートアップをやり続けていく中で、共に成長していくということにやりがいを感じてきたし、一度終わらせて2周目という発想は僕にはない。このメンバーは今この時しか集まれなかったからこうやって今も泥臭くやれている。
もう1つは、このスタートアップの市場環境がどんどん良くなっていく中で、ROXXも累計35億円もの外部資本を集め、成長に使わせていただいた以上、必ずリターンを出さなければならない。一方で出資いただいた際の時価総額を超えるM&Aは現実的に考えづらかった。それはもちろん未上場の市場全体が加熱し、株式市場とのプライシングに大きな乖離があったということでもありましたが、その2つの状況からも自ずと上場を目指していました。
――上場後は先行投資による赤字決算が続いています。特に今期(※2025年度・上場した初年度)はマス広告に大きく投資することにしました。グロース市場、特に赤字上場組に対する視線が厳しくなる中、上場初年度の投資判断について教えてください。
結論から言うと、中長期に事業が成長しなくなることは上場会社の経営として明確に失格です。だから目の前の投資は継続させ、中長期でより大きく持続的に成長をさせる戦略をとっています。一方で、株価が公募価格を割っていることに対する心苦しさは今でも非常に強く感じてます。大きく成長するために必ず必要だと分かってやっているけれど、それは楽ではない。長い時間をかけて正解にしていかなきゃいけないと考えています。
Q4. AI時代における労働集約型ビジネスの可能性

データを持つ大手こそが最強になる時代
――AIの進化により、既存のインターネット・ビジネスが大きく変わろうとしています。この中においてROXXが手がけるHR領域の労働集約型ビジネスモデルをどう捉えていますか。
実はいま積極的に取り組んでまして、今までウェブサービスではなかなか踏み込めなかった労働集約的な領域と、LLMの相性は非常にいいと思っています。今までのスタートアップが頑張ってきた領域とは違うところに大きなチャンスがあると捉えてます。
ROXXが提供する「Zキャリア AI面接官」では、企業の面接官の代わりに、AIが求職者との面接を24時間やっています。リアルでの面接と違って日程調整したり、わざわざ移動するような時間がかからないので、桁違いに選考が短くなります。しかも若い人ほど「AIの面接の方がいい」と言うんです。緊張しないし、わざわざ先の予定を考えなくていい。これまでの採用面接に慣れた世代にとっては「こんなもので落とすな」と思うかもしれないですが、若いデジタルネイティブ世代がいるし、採用企業にとっても求職者にとっても、明らかにAI面接の方が効果が大きい。
――具体的にはどのようなAI活用をされているのでしょうか。
AI面接官以外には、求職者とLINEのやりとりにおいて、どういう会話をすれば面談につながるかを学習させたり、架電業務の一部も自動化しています。でも、それができるのは労働集約がベースにあるからです。
データを持っている大手が一番強いとこの市場では捉えています。LLMを使えば同じようなツールはすぐ作れてしまうからこそ、学習データの総量と、それらを活用していち早く使ってくれる人を取り込めるかで、後から取り返しがつかないぐらい指数関数的に差が開く。
年間何百人、何千人という採用活動を行う企業が主要顧客だからこそ、大量の学習データを武器に勝ち切れる可能性を信じています。
Q5. 組織拡大での課題と社外取締役の役割

「止めてくれる人」を自分から求めに行く
――テクノロジードリブンなback checkと、その正反対に位置するZキャリアという二つの事業を運営しています。従業員数が290名まで拡大する中、マネジメント面での課題はありますか。
学んだのはやはり事業ごとに全く違う組織だったということ。back checkとZキャリアで、立ち上げた当時は違うものを2つ経営しているような状況で苦労しました。僕自身もテックドリブンなサービスはどうしても自分が得意じゃないことをやっている感覚がありました。
一方で、Zキャリアは自分の身近な環境でやっているサービスなので感覚的にいける。今は違う事業フェーズで、違う組織文化をコントロールしなきゃいけないという課題は解決されています。
――公開企業におけるガバナンスが注目されています。改めて取締役会や社外取締役の役割をどう捉えていますか。
この先、今このフェーズだったらどうなるかということを想像できる人を社外取締役に迎え入れなければいけない。我々はどうしても短期の問題に目が行きがちで、まだ不慣れな部分があります。より中長期的な視点や、行き過ぎたものを抑制するという意味で、これまでの経験に基づいた、正しさを一緒に考えてくれる存在のありがたみはめちゃくちゃ感じました。
自分にとって耳が痛いことを言ってくれる、自分を止めてくれる人がいないと会社は良くならない。背伸びしなきゃいけないし、大きく成長させ続けないといけないから、どういうボードチームを作れるかは経営者の力量です。
福留大士さん(チェンジホールディングス代表)が長らくその役割をしてくださっていて、行き過ぎた期待に対しては冷ます必要があるし、僕らもついつい「これぐらい行きたい」って言ってしまうこともありますが、「その先はどうなるんだ」って、より長い時間軸で見てくれる。同じ責任を経験された方だからこそ、的確なアドバイスをいただけます。



